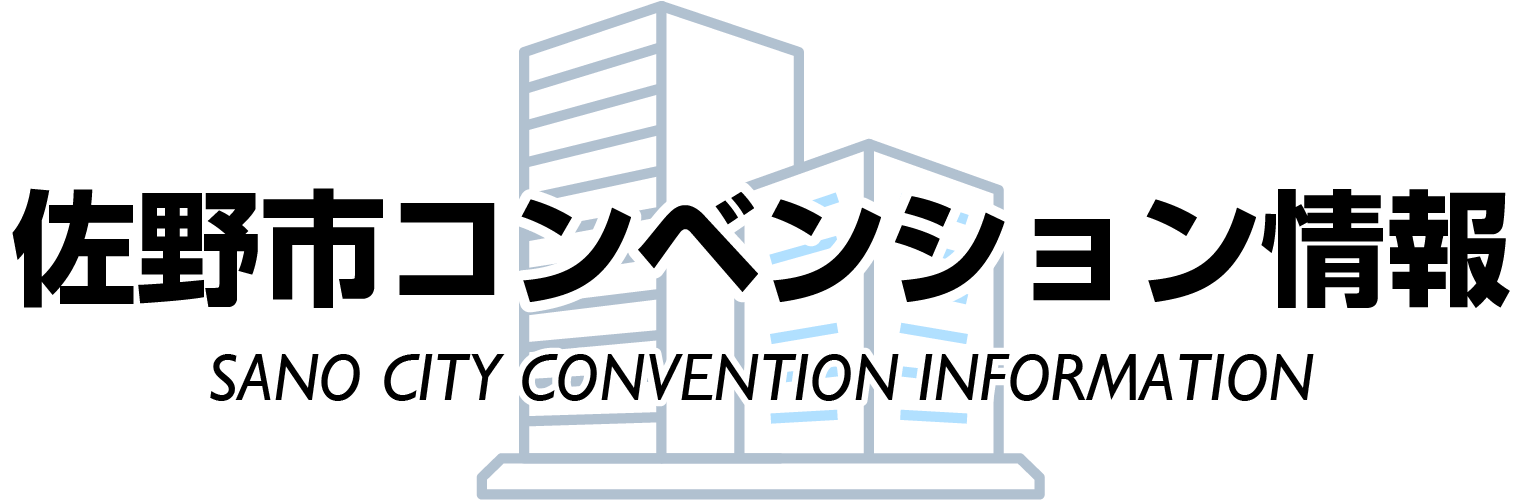「西の芦屋、東の天明」と言われた鋳物。佐野市に1100年以上続く天明鋳物は、現在も佐野市の中心市街地「まちなか」に多く残されています。本コースでは、現在も続く鋳造所やかつての鋳造所跡、天明鋳物が残っている場所をめぐります。
佐野駅

佐野厄除け大師の門前町として栄えた佐野市の代表駅で、JR東日本の両毛線と、東武鉄道の佐野線が乗り入れる接続駅。駅南口の広場には同市のマスコットキャラクター「さのまる」を天明鋳物でかたどった象が設置されています。
栗崎鋳工所

風鈴や置物などお土産にぴったりの品物が並びます。中でもメディア取り上げられることも多いベーゴマは必見。
日本基督教団佐野教会・鐵館

キリスト教プロテスタントの教会。昭和9年に建築された木造2階建で切妻造、外装下見板張があるのが特徴。1階が幼稚園の園舎、2階に礼拝堂という形式をとっており、平成4年までは教会附属みくに幼稚園舎としても使用されていました。正面には丸窓と左右対称に配置された尖頭アーチ型の窓があり、ゴシック風の造りとなっています。
正田鋳造所

古来より天明鋳物の町として全国に名を知られた佐野。古天明湯釜の雅趣に富んだ鋳法と技術は西の芦屋、東の天明と茶人に愛好されました。現当主は29代目で「紫銅焼き」が特徴。※見学の受付はしていません。
若林鋳造所

弘化3年(1846年)創業。当主若林秀真氏は5代目天明鋳物師。伝統的技法により、唐澤山神社拝殿の神鈴、奈良東大寺の茶之湯釜「大佛釜」などを制作。同所に収蔵保存されてきた天明鋳物生産用具が栃木県指定有形文化財に指定されました。
太田邸

江戸時代末期に建てられた黒漆喰壁の旧店舗。市の文化財に指定されている。
寺岡邸

糸問屋として建てられた大規模な商家。最近まで労働金庫の店舗として使われていた。昭和3年築。
佐野市観光物産会館

佐野厄よけ大師入口正面にある物産館です。お土産用佐野らーめん、そば、耳うどん、お菓子、地酒、天明鋳物などの伝統工芸品、さのまるグッズ、地元で採れた新鮮野菜など、幅広く取り揃えています。
佐野厄よけ大師

天慶7年(944年)奈良の僧宥尊上人が開いた寺。厄除け元三慈恵大師を安置して、厄除け、方位除けの祈願を続けています。正月になると大祭を開催し、厄除けをはじめ、身体安全や心願成就などのご利益があるパワースポットです。また、徳川家康の遺骨を久能山から還葬の際、この寺に一泊するなど、徳川幕府との縁も深いところです。
観音寺

真言宗豊山派の寺で、佐野市指定文化財となっている「佐野大仏」や佐野七福神「大黒天」を祀っています。本堂前にある銅造阿弥陀如来坐像(佐野大仏)は、江戸時代初期における天明鋳物の名作です。
味噌まんじゅう新井屋

旧土佐薬局の建物で現在は店舗として利用されています。隣地との間にはうだつと呼ばれる防火壁(財力の象徴)があります。明治3年築。
| 名称 | D. 観光ボランティアガイドがご案内するまちなか探訪 |
|---|---|
| 所要時間 | 約3時間 |
| コース詳細(例) | 佐野駅⇒栗崎鋳工所⇒日本基督教団佐野教会⇒鐵館⇒正田鋳造所⇒若林鋳造所⇒太田邸⇒寺岡邸⇒佐野市観光物産会館⇒佐野厄よけ大師⇒観音寺⇒味噌まんじゅう新井屋⇒佐野駅 |
| 問合せ先 | (一社)佐野市観光協会 |
| 電話番号 | 0283-21-5111 |